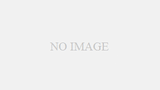もうすぐお子さんの保育園や幼稚園への入園を控え、期待と不安が入り混じった気持ちのママもいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、育休復帰をするママさんは、
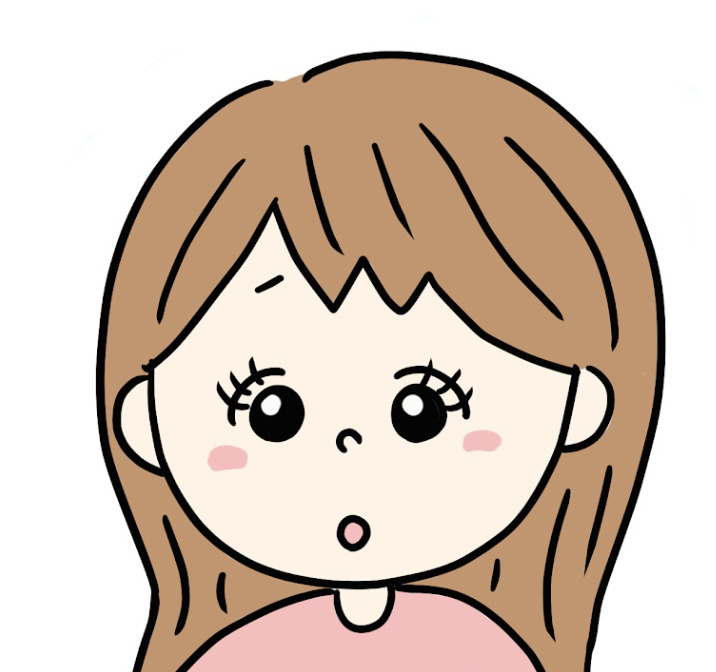
久しぶりにちゃんと仕事ができるのかな……
職場の人がどう自分を迎え入れてくれるのかな。
など、不安に思うことも多いでしょう。
そこで1つ、ぜひ知っておいていただきたいの「保育園の洗礼」です。保育園の洗礼とは、入園後にお子さんが頻繁に感染症にかかる現象を指します。
全体のクラスの中でも、特に免疫力の弱い0歳児クラスは、「保育園の洗礼」で、最初のうちは何度も呼び出しを受ける可能性が高いです。
実際に、東京女子医科大学(※1)の研究では、0歳児の年間病欠日数は最も多いとされています。
また、別の調査(※2)では、保育園に通い始めた子どもの約81%が、4月から6月の間に風邪で保育園を休ませた経験があると報告されているのです。
「保育園の洗礼」は避けられない部分もあります。
とはいえ、準備しておけることや予防できることもあるので、育休復帰をするママたちが少しでも前向きな気持ちで過ごせるように、本記事では「保育園の洗礼」の対策や預け先の知識をご紹介します。
この記事を読むと分かること
▶️保育園の洗礼の対策方法
▶️子どもが病気が続いたときの預け先や休暇についての知識
※1 野原 理子・冨澤 康子・齋藤加代子「保育園児の病欠頻度に関する研究」, 平成27年, p149
※2 パパ・ママにとっては常識!?80.9%が経験する「保育園の洗礼」とは?
保育園の洗礼とは
保育園の洗礼とは、ずばり、入園後短期間に子どもが感染症を繰り返すことです。特に、入園して間もない「慣らし保育中」になることが多いと言われています。
今まで家庭で過ごしていた子どもが、保育園でさまざまな菌やウイルスと出会うことで、発熱・鼻水・咳・下痢など、ざまざまな症状の感染症にかかるのが保育園の洗礼です。
中には、全くかからなかったという話し(独自の集計では10%のご家庭)も聞きましたが、高確率でほとんどのお子さんが保育園の洗礼を受けることになります。
実際、私が受け持っていた0歳児クラスでは、5人全員がいつも何かしらの感染症にかかっており、入園後半年ほどは、全員揃う日はほとんどありませんでした。
私の息子も6ヶ月のときに入園しましたが、4ヶ月ほどは、毎月5日通園できればいいというレベルで体調を崩していました……。本当にしんどかったです!
保育園の洗礼はいつまで続く?
保育園の洗礼はいつまで続くのか気になるところだと思います。明確な根拠は見つけられませんでしたが、まるり先生の経験上は、半年ぐらいで落ち着いてくる印象です。
ある調査では、入園後7か月から1年で症状が落ち着いたという報告が多く見られました。実際に私の息子も半年ほど経った頃から、ほとんど毎日保育園に通えるようになりました。
ただし、保育園の洗礼が終わったとしても、※1の研究によると、7月と12月には感染症が増加することや、年間を通して0歳児の病欠日数が最も多いことが示されています。つまり、保育園の洗礼が終わっても0歳児のうちは感染症にかかる確率は高いというわけです。
※1 野原 理子・冨澤 康子・齋藤加代子「保育園児の病欠頻度に関する研究」, 平成27年, p149
保育園時代にたくさん風邪をひくと、小学生になったらひきづらくなる?
保育園での感染症に不安を覚える方もいるかもしれません。しかし、「保育園時代にたくさん風邪をひくと、小学生になったらひきづらくなる」という嬉しいニュースもあります!
あるアメリカの調査(※2)では、大規模保育園に通っていた子どもたちは自宅保育の子どもたちと比較して、2年目に頻繁に風邪をひきましたが、6年目になると風邪をひく頻度が減ったという結果が示されています。
この結果からは、保育園時代に風邪をひいて免疫を獲得することで、小学生ごとになると風邪への耐性が高くなることが分かります。
とは言っても、病気ばかりで保育園に通えなかったら、仕事を続けられないかもしれない……と不安に思うのは当然のことです。その不安を完全に払拭することは難しいですが、最低限、子どもの病気が続いたときの預け先や休暇について知っておく必要はあります。
後ほどご紹介します。
※2 Influence of Attendance at Day Care on the Common Cold From Birth Through 13 Years of Age, 2002
保育園の洗礼に備えて準備しておくと良いもの
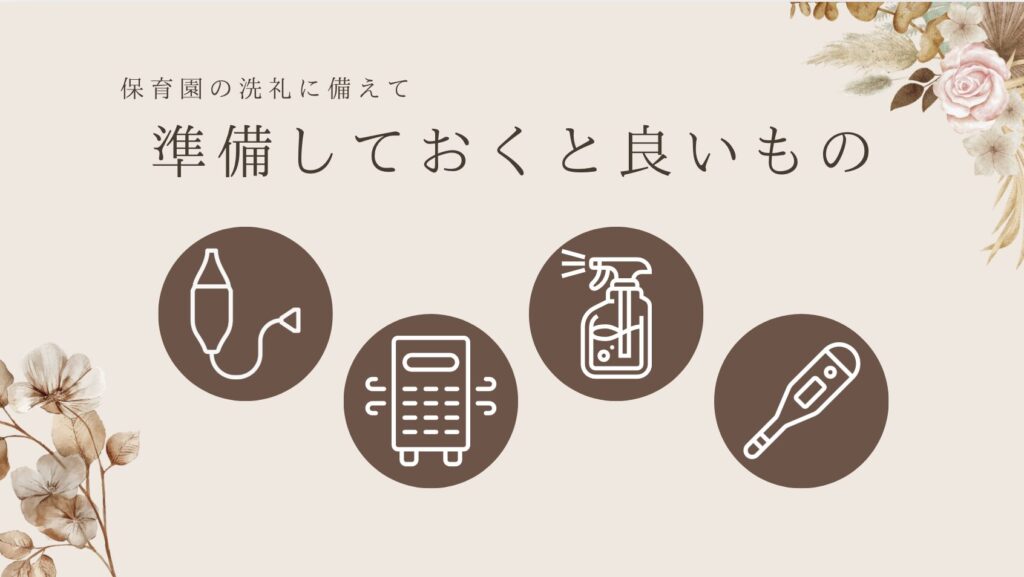
保育園に通い始めると、多くの子どもたちが「保育園の洗礼」と呼ばれる頻繁な体調不良を経験をすることがよく分かりましたね。保育園の洗礼を受けるにあたって、実際に私が重宝したアイテムをご紹介します。参考にしていただけると幸いです。
1. 電動鼻水吸引器(メルシーポット)
子どもは自分で鼻をかむことが難しく、鼻水が溜まると中耳炎や咳の原因になることがあります。電動鼻水吸引器は、鼻水を効果的に除去し、症状の悪化を防ぐのに役立ちます。
鼻吸い器の中でも、特に「メルシーポット」は多くのママたちから支持されています。実際に私も、先輩ママから教えてもらって以来愛用していますよ。
また、自分の鼻詰まりがひどいときにはノズルを変えて使用できるので、とっても便利です!!
空気清浄機
室内の空気環境を整えることで、感染症の予防に役立ちます。
特に、加湿機能付きの空気清浄機は、適切な湿度を保ち、ウイルスの活動を抑制する効果があります。部屋の広さや機能性を考慮して、適切な製品を選びましょう。
我が家はシャープの空気清浄機2台体制です!
2. 体温計
毎朝の検温は保育園生活の一部です。個人的には非接触型体温計や赤ちゃん用体温計だと正確性に欠けると感じているので、大人用の一般的な体温計を準備しておくことをおすすめします!我が家で使ってるのはこれ。
医療用アルコール
手指の消毒や、ドアノブ、テーブルなどの共用部分の除菌に使用します。外出先から戻った際や食事前後など、こまめな手指消毒を習慣づけることで、感染症の予防に効果があります。
子どもの手の届かない場所に保管し、使用時には適切な量を守るよう注意しましょう。インフルエンザの時に特に重宝しました……
ハイター
おもちゃや食器の消毒に使用できます。適切な濃度に希釈し、対象物を浸け置きした後、十分に水洗いすることで、細菌やウイルスの除去が可能です。
使用方法や希釈濃度は製品の指示に従い、安全に取り扱うことが重要です。感染症によってはアルコールが効かない場合もあるので、ときと場合によって使い分けましょう!
以上のアイテムを準備しておくことで、保育園生活のスタートをよりスムーズに迎えることができると思います!
子どもの病気が続いたときの預け先や休暇について知っておこう
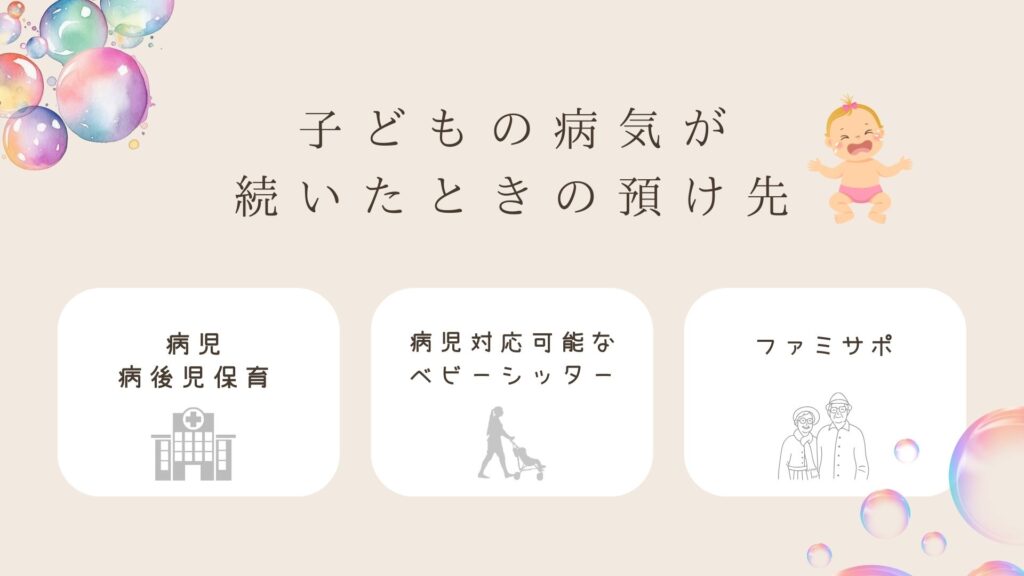
子どもの病気が続いたときの預け先や休暇についてご存知ですか?
基本は、両親が休んで対応することが多いかと思いますが、どうしても両親どちらも休めなかったり、親族の協力も得られなかったりする場合もありますよね。
そんなときに利用できる病気の子どもの預け先は、主に以下の3つです。
- 病児・病後児保育
- 病児対応可能なベビーシッター
- ファミリー・サポート・センター
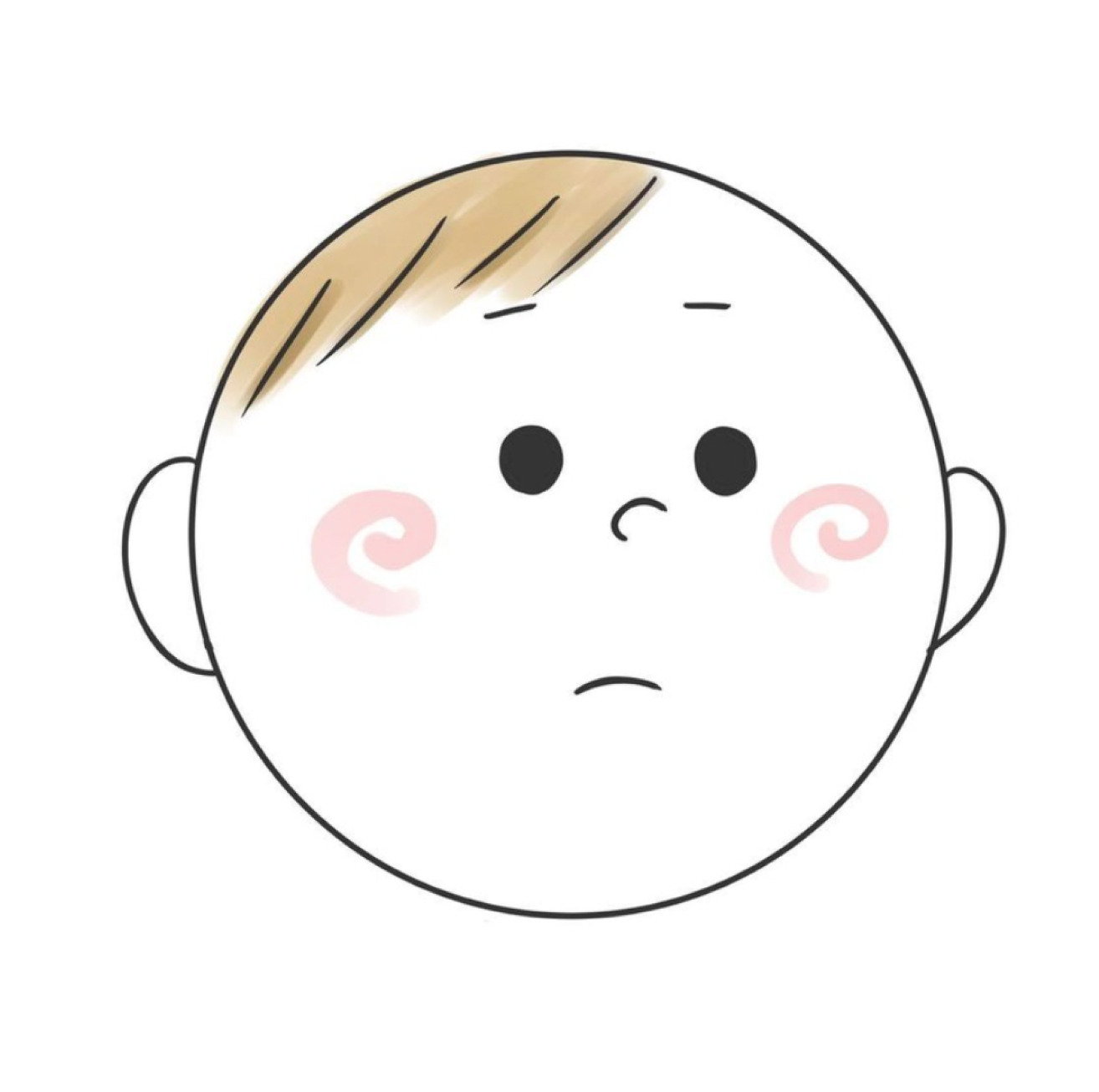
どのサービスも、実際に使わなかったとしても、いざというときに利用できるように、事前登録は済ませておくのがベター!登録に時間を要するサービスもあるので、その点は注意してくださいね。
それぞれのサービスについて、以下で詳しく解説します。
病児保育
病児保育事業は、厚生労働省の資料(※3)によると、以下のように定義されています。
子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる環境整備を図る。
病児保育事業(厚生労働省)p23
病児保育事業の種類は、以下3つです。
- 病児対応型・病後児対応型
- 体調不良児対応型
- 非施設型(訪問型)
ここでは、3つのなかでも最もスタンダードな「病児対応型・病後児対応型」について解説します。
地域の病院や保育所施設などに設置されている専用のスペースで、看護師などが一時的に病気の子どもを保育する病児保育事業。
【主な対象児童】
急変する可能性は低い
病気が回復しておらず集団保育が難しい
保護者の仕事の都合で家庭で保育するのが難しい
市町村が必要と認めた10歳未満の子ども
※上記全てを満たしているもの
※自治体・施設によって条件が変わる
利用できる病児・病後児保育施設は、住んでいる自治体によって変わります。上記対象児童の条件も施設によってさまざまなので、事前に確認しておきましょう。利用できる施設は、住んでいる自治体のホームページや子育ての担当窓口などで確認できます。
利用の仕方もさまざまですが、基本的には、指定の医療機関で受診後、必要書類を揃えて申し込む必要があります。
事前登録が必要な施設も多いため、利用する可能性がある場合は、住んでいる自治体の病児保育施設を探して、入園前に登録を済ませておきましょう!
病児対応可能なベビーシッター
対応可能な地域や病状であれば、ベビーシッターも利用できます。
KIDNAシッターやキッズラインなどの各種ベビーシッターサービスから予約可能です。ただし、事前にシッターさんとの面談が必要な場合もあるため、急遽利用したいときに備えて、事前に確認しておきましょう。
また、病児保育やファミリーサポートに比べると、かなり料金が割高です。
とは言っても、料金が高いぶん、1対1で手厚く関わってもらえるのが、ベビーシッターのいいところ。自宅で見てもらえるのも安心できるポイントです。さらに、保育のプロが見てくれるので、安全面も弱っている子どもの精神面のフォローも安心して任せられるでしょう。
ファミリー・サポート・センター
ファミリー・サポートは、地域の中で「サポートをする人」が「サポートを受けたい人」に、子どもの送迎・預かりなどの援助を行う有償ボランティアです。
基本的に1時間1,000円前後で利用できますが、保育のプロではない方も多いため、安全面や知識面では若干不安があります。また、事前の説明会への参加・顔合わせなど、利用するまでに時間を要することもあるため、利用を検討している場合は、早めの行動が必要です。
病児保育の実施の有無は自治体によって違うので、事前に担当窓口へ確認しましょう。
看護休暇を取得する
「子の看護休暇」は、子ども(6歳未満)の発熱・怪我により、看病が必要になった場合に取れる「法定休暇」です。病気になったときだけではなく、健康診断・予防接種のために取得することも認められています。
ただし、以下のように「子の看護休暇」の申し出に対して、会社側が拒否できるケースもあるので注意しましょう。また、賃金の発生の有無は会社が自由に決められるので、無給となる場合もあります。
参考:厚生労働省「介護休暇・子の看護休暇の時間単位取得について」(令和2年)
厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」(令和3年)
保育園の洗礼の対策方法3つ
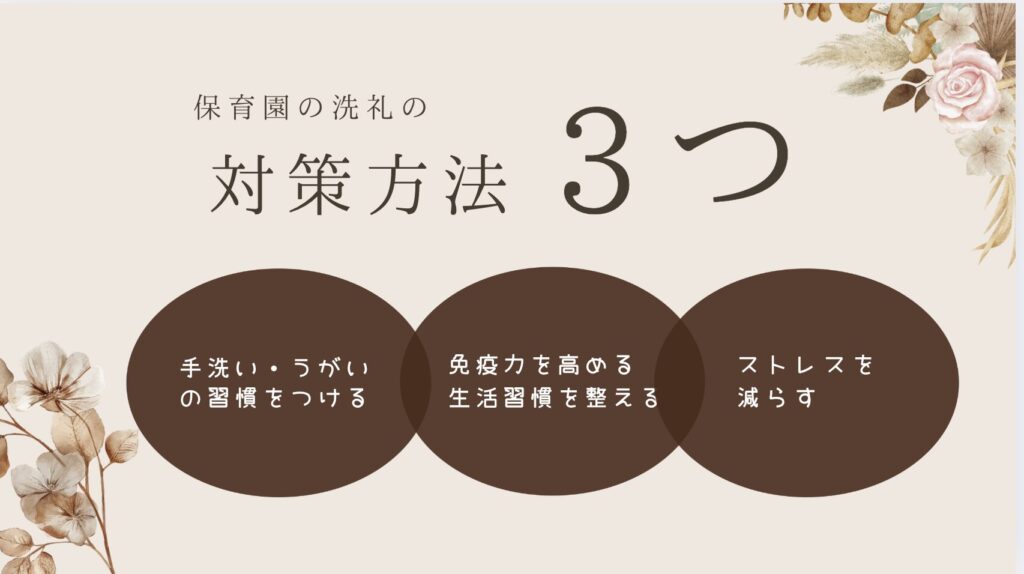
保育園の洗礼を受けることは多くの親にとって不安な時期ですが、事前にできる予防策を講じることで、少しでも負担を軽減することができるかもしれません。
以下に、保育園に通い始めたお子さんが感染症にかかりにくくするための予防策を紹介します。
手洗い・うがいの習慣をつける
お子さんが保育園で多くの物に触れることを考えると、手や顔を清潔に保つことは非常に重要です。家で手洗いやうがいの習慣を身につけることで、感染リスクを大幅に減らすことができます。
国立成育医療研究センターによれば、石鹸やハンドソープを使用した手洗いは、ウイルス量を大幅に減少させる効果があると報告されています。
特に、食事前やトイレの後、外から帰宅した際には、20秒以上かけて丁寧に手を洗うことが推奨されています。
・参考サイト
国立成育医療研究センター「正しい手洗いの方法」
テルモ体温研究所「感染症予防の基本は、手洗いとマスク」
免疫力を高める生活習慣を整える
保育園の洗礼を予防するためには、免疫力を高める生活習慣を整えることも大切です。
免疫力を高めるためには、バランスの取れた食事や十分な睡眠が不可欠です。ビタミンCやビタミンDは、免疫機能の維持に重要な役割を果たします。ビタミンCは抗酸化作用を持ち、免疫細胞の機能をサポートします。
これらのビタミンを多く含む食品を日常の食事に取り入れることで、免疫力の向上が期待できるでしょう。
・参考サイト
日本微量栄養素情報センター「免疫システムの概要」
Kao「ビタミンと免疫」
ストレスを減らす
ストレスが免疫機能に悪影響を与えることは、多くの研究で確認されています。特に、慢性的なストレスは免疫系を弱め、感染症にかかりやすくなることがあるのです。
お子さんがストレスの少ない環境で過ごすことが、免疫力を高めるために役立つと考えられています。リラックスできる時間を設けたり、十分な休息を取ることが重要です。
保育園の洗礼の対策方法を知って、慣らし保育に備えよう!
子どもの病気が続いたときの預け先や休暇などについてご紹介しました。これから新しい環境に飛び込んでいく私たち。不安ばかり……というママさんも多いと思います。
保育園の洗礼について、事前に職場に話しておくのも良いかもしれませんね。職場によっては冷たい態度をとってくる人もいるかもしれませんが、気にする必要はありません。
働きながら子どもを育てる権利は、誰にでもあります。病気にかかってしまう子どもも、親のあなたも悪くありません。冷たい態度をとる職場の価値観が間違っているのです。
昔に比べたら働きやすくなったのかもしれません。しかし、家庭や子どもを大事にしたいという想いを理解してくれない職場も、少なからずあります。実際に、私の夫の職場もそうです。育児休暇も取れず、残業ばかりの毎日を過ごしています。もっと働く親に優しい世の中になって欲しいと願うばかりです。
肩身の狭い思いをするママやパパが少しでも減るように、子どものことを目一杯愛せるように。微力ながら、これからも発信を続けていきたいです。
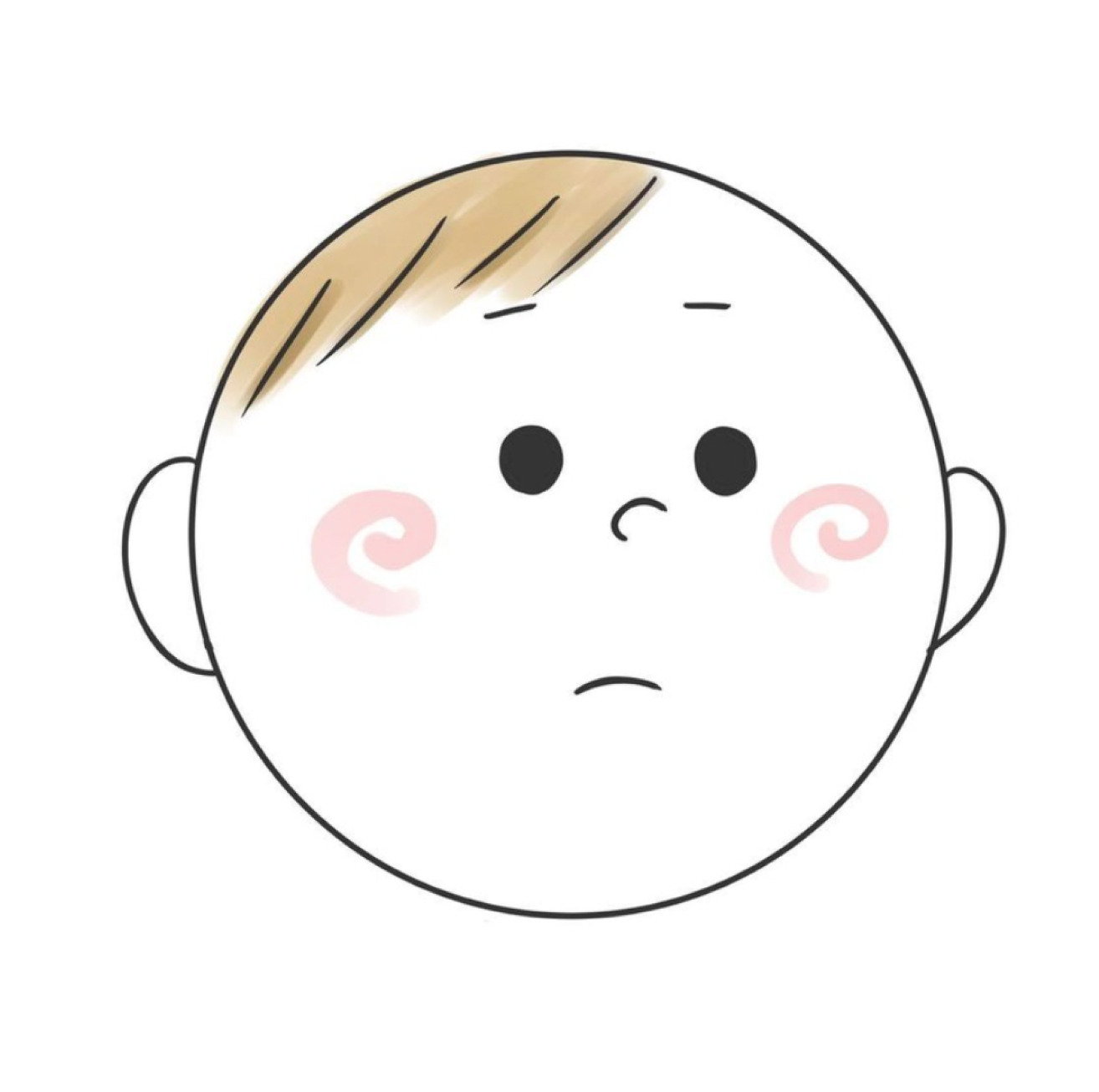
4月からのスタート、一緒に頑張りましょうね!